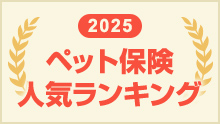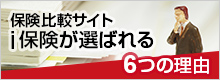ペット保険お役立ち情報
ペット保険の告知義務とは?「バレない」は危険!
申告の注意点

更新日:
ペット保険への加入を検討する際に、意外と見落とされがちなのが「告知義務」です。「少しごまかしてもバレないのでは?」と思っている方もいるかもしれませんが、虚偽告知は後でバレるリスクが高く、保険金が支払われなかったり、契約解除になるケースも少なくありません。
告知義務を正しく理解し、ペットの健康状態をきちんと伝えることは、いざという時にしっかり補償を受けるために欠かせない大切なポイントです。
この記事では、告知義務の仕組みや「バレない」は危険な理由、正しく申告するためのポイントをわかりやすく解説します。大切な家族であるペットを守るために、トラブルを防ぎ、安心して保険を選ぶ参考にしてください。
- 目次
ペット保険の告知義務とは?
告知義務の意味と仕組み
ペット保険における「告知義務」とは、ペット保険に加入する際に保険会社に対して契約者である飼い主さんが、ペットの基本情報や健康状態を報告する義務のことです。人間の生命保険や医療保険と同様に、ペット保険でも契約時にペットの現在の健康状態や過去の病歴を正確に申告する必要があります。
告知義務は保険法によって定められており、保険会社が指定した項目について、契約者は事実を正確に報告しなければなりません。この制度により、保険の公平性と健全な運営が保たれています。
- 保険法における告知義務
-
保険法 第四条(告知義務)
保険契約者又は被保険者になる者は、損害保険契約の締結に際し、損害保険契約によりてん補することとされる損害の発生の可能性(以下この章において「危険」という。)に関する重要な事項のうち保険者になる者が告知を求めたもの(第二十八条第一項及び第二十九条第一項において「告知事項」という。)について、事実の告知をしなければならない。
なぜ正確な申告が求められるのか
ペット保険はそもそも「健康である状態」のときに万が一の事態に備えて加入するものです。そのため、実は病気であったり、気になる症状があるなどの状態になってから、新たに加入するペットが増えると、保険制度自体が成り立たなくなってしまいます。
ペット保険は、加入者同士の助け合いのもと成り立っているものです。持病のあるペットや治療中のペットと健康なペットが同じ条件で加入することは公平とは言えず、保険料の公平性を保つために正しい告知が必要となります。
告知が必要な健康状態や既往症の範囲
告知が必要な内容は、最近の通院歴や慢性疾患、過去の手術歴など保険会社ごとに異なります。
一般的に以下のような内容について申告が求められます。
| 現在の健康状態 | 治療中のケガや病気、 投薬の有無 |
|---|---|
| 過去の病歴 | これまでにかかった病気や ケガの履歴 |
| 手術歴 | 去勢・避妊手術を含む すべての手術履歴 |
| 健康診断の結果 | 異常が見つかった場合の詳細 |
| ワクチン接種状況 | 混合ワクチンや 狂犬病ワクチンの接種履歴 |
| その他の健康に 関する事項 |
獣医師から指摘された 症状や所見 |
「軽微な症状だから」「一時的なものだから」という自己判断は危険です。軽微な症状であっても、獣医師が診断した内容は重要な情報です。健康状態や既往症について確認を求められる場合は、すべて正確に申告することが重要です。
「バレない」は危険!虚偽告知がバレる理由
「バレないから大丈夫」と思って虚偽の告知をすると、後で保険金が支払われなかったり契約が解除されたりするリスクがあります。ここでは、保険会社がどのように告知内容を確認するのか、虚偽申告がバレる理由とその仕組みを詳しく解説します。
ペット保険会社が確認する情報
ペット保険の告知に関する調査はプロによって厳しく行われます。
保険会社は以下のような方法で告知内容の真偽を確認します。
- 動物病院への照会
- 診療記録や
検査結果の確認
- 保険金請求時の詳細調査
- 治療内容と
過去の病歴の照合
- 専門調査員による調査
- 疑いがある場合の
徹底的な調査
- データベースとの照合
- 他社での契約状況や
請求履歴の確認
動物病院の診療履歴や健康診断の影響
動物病院では、すべての診療記録が詳細に保管されています。保険会社は保険金請求時や契約審査時に、これらの記録を確認する権限を持っています。
保険金請求をした病気が、その時の通院理由とは異なるものでしたが、告知義務違反で解除通知が届き、保険を解約されてしまったという実例もあります。
特に以下のような情報は一般的に記録として残り、後に発覚する要因となります。
| 診療記録 | 症状、診断名、 処方薬、検査結果 |
|---|---|
| カルテ情報 | 獣医師の所見や治療方針 |
| 検査データ | 血液検査、レントゲン、 エコー検査の結果 |
| 処方箋記録 | 薬剤の種類、 投与期間、投与量 |
保険金請求時の調査でバレるケース
保険金請求時には、治療内容と過去の病歴との関連性が詳しく調査されます。保険会社の調査があり過去の病歴が発覚したという事例が報告されています。
告知義務違反がバレるパターンには以下のような例があります。
関連疾患の発症
告知しなかった既往症が悪化した場合
継続治療の発覚
加入前から続いている治療が判明
検査値の異常
過去の検査結果との矛盾が発見
第三者からの通報
嘘の告知は、加入時や保険金請求時だけでなく、第三者による通報によってバレることもあります。
告知義務違反のリスクとペナルティ
告知義務を守らずに加入すると、保険金が支払われないだけでなく、契約解除や今後の保険加入が難しくなるなど、深刻なペナルティが発生する可能性があります。ここでは、ペット保険の告知義務違反による具体的なリスクと注意点を詳しく解説します。
保険金が支払われないケース
告知義務違反が発覚した場合、最も大きな影響は保険金の支払い拒否です。通院歴や手術歴などについて虚偽の告知をした場合「告知義務違反」となり、保険金を受け取れなかったり、契約解除となります。
具体的には以下のような状況で保険金が支払われません。
告知義務違反に関連する疾患
例えば、以前から皮膚病を患っていたのに申告せず加入した場合、その病気や関連するアレルギー症状での診療費は保険金の支払い対象外になる可能性があります。保険会社は診療履歴をもとに「既往症による発症」と判断し、補償を拒否されるケースが多いです。
因果関係が疑われる疾患
告知しなかった症状が関係している可能性があれば、直接同じ病気でなくても保険金が支払われないことがあります。例えば、過去の関節炎を申告せず加入後に歩行困難になった場合、因果関係を指摘されて支払いを拒否されるケースがあります。
全額の支払い拒否
特に悪質な告知義務違反と判断された場合は、申告しなかった病気に限らず、他のケガや病気の診療費も全額支払いを拒否されることがあります。これは「保険制度の公平性を著しく損なう」と判断され、厳しい対応を取られるケースです。
契約解除・既払い保険料の扱い
告知義務に違反しているのですから当然ですが、保険法の第二十八条の通り、契約が強制的に解除される可能性があります。解除されれば、それまでに支払っていた保険料は多くの場合、返還されません。
- 保険法における告知義務違反による解除
-
保険法 第二十八条(告知義務違反による解除)
保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。
契約解除の影響は以下の通りです。
強制解約
保険会社の判断で一方的に契約を終了されます。告知義務違反が発覚した時点で、たとえ保険料を支払い続けていたとしても契約は無効とされ、以降の補償も一切受けられません。
支払った保険料の損失
ペット保険は掛け捨て型が一般的で、解約時に保険料の返金はほとんどありません。告知義務違反によって解約されると、それまで支払っていたお金が無駄になってしまいます。
将来の補償の喪失
若いうちに契約解除となると、その後高齢になったペットに対する補償を確保できなくなるリスクがあります。特にシニア期の診療費は高額になるため、保険が使えないダメージは大きいです。
他社への加入が難しくなるリスク
告知義務違反による契約解除の記録は、保険業界内で共有される場合があります。これにより、以下のような影響が生じる可能性があります。
他社での加入審査に影響
保険会社間で情報が共有されることがあり、過去に告知義務違反で契約解除された履歴があれば、他社の加入審査でも不利になります。
加入条件の厳格化
仮に加入が認められても、通常より高い保険料や限定補償など、条件が厳しくなる場合があります。告知内容への審査もより詳細に行われるでしょう。
加入自体の拒否
最悪の場合は、過去の告知義務違反を理由に新規契約自体を断られることもあります。高齢のペットや持病を抱えるペットでは、代替の選択肢がほとんどなくなるリスクがあります。
正しく告知するためのポイント
正確な告知を行うためには、以下のポイントを押さえましょう。
ポイント 1告知の回答は事前準備と正確さを大切に
記録の事前準備
| 診療記録の整理 | 過去の通院歴、診断名、 投薬の有無 |
|---|---|
| ワクチン接種記録 | 接種日、ワクチンの種類、 接種した動物病院 |
| 薬歴の確認 | 処方された薬の名前、 期間、用量 |
- 回答時の注意点
-
- 正確な日付:「〇年頃」ではなく、できる限り正確な年月日を回答
- 診断名の正確な回答:自己判断ではなく、獣医師の診断名をそのまま回答
- 症状の詳細:「元気がない」など抽象的ではなく、具体的な症状や状態を回答
ポイント 2健康状態を正確に伝えるコツとは?
過去の治療歴を正確に把握すること、そしてありのままに回答する、という点がとても重要です。大切なペットの健康状態を把握するためにも動物病院にかかった日、内容などはメモ帳に記載しておいて、正確に告知を行いましょう。
健康管理記録の作成
| 日常の体調変化 | 食欲、排泄、 行動の変化を記録 |
|---|---|
| 通院履歴 | 動物病院名、受診日、 診療内容、費用 |
| 薬剤投与記録 | 処方薬、サプリメント、 予防薬の使用履歴 |
- 曖昧な表現に注意
-
曖昧な表現にしない、自己判断をしない、という点も重要です。以下のような曖昧な表現は避け正確な表現をするようにしましょう。
- 「たしか~だったと思う」→ 正確な日付や内容を調べて回答
- 「軽い症状だったので」→ 症状の程度は獣医師の判断に委ねる
- 「一時的なものだったから」→ 継続性に関わらず事実を回答
ポイント 3告知内容に不安があれば保険会社に相談を
告知内容について不明な点がある場合は、保険会社へ直接相談をしましょう。
各社のお問合せ先は「保険会社からペット保険を選ぶ」の保険会社一覧ページより各社のお見積りボタンを押下してご確認ください。
必要に応じて獣医師と連携し、かかりつけの獣医師に告知内容の確認をしてもらうと安心です。
ペット保険を安心して選ぶために
告知義務条件は保険会社ごとに違う
ペット保険会社によって、告知を求める項目や条件は大きく異なります。2026年現在、主要な保険会社の告知義務の特徴は以下の通りです。
告知項目の違い
| 基本項目 | 年齢、品種、体重、 ワクチン接種歴(全社共通) |
|---|---|
| 病歴の範囲 | 過去1年~3年間の病歴 (会社により異なる) |
| 症状の詳細度 | 軽微な症状まで含むか、 重大な疾患のみか |
審査基準の違い
| 年齢制限 | 新規加入可能年齢の上限 ワクチン接種歴(全社共通) |
|---|---|
| 品種特有疾患 | 特定品種で多い疾患への対応 |
| 既往症の扱い | 治療中や過去に罹患した病気があっても、条件付きで加入できるケースがあります。 条件とは、ペットが現在かかっている病気や以前罹った病気を補償の対象外にするというものです。 |
補償内容や保険料も比較しよう
ペット保険に加入する際は告知義務の条件だけでなく、以下の要素も総合的に比較することが重要です。
補償内容の比較をしよう
保険会社によって補償内容は異なります。特に以下の点の違いを確認してご自身にあった保険を検討しましょう。
- 補償割合:50%、70%、90%、100%など
- 年間限度額:年間の補償される診療費の上限額
- 免責金額:自己負担額の有無
保険料の比較をしよう
必要な補償内容を確認したら、保険料の違いを確認しましょう。割引制度やキャンペーンを実施している保険会社もあります。
- 保険料:ペットの種類、年齢、品種、補償内容による差
- 保険料の上昇:加齢による更新時の保険料の変化
- 割引制度・キャンペーン:インターネット申込割引、多頭割引やプレゼントキャンペーンなど
サービス内容などその他の項目で比較しよう
保険会社によって付帯サービスや保険料の払込方法などにも違いがあります。補償内容や保険料の他にこのようなサービスを比較するのもよいでしょう。
- 保険料の払込方法:クレジットカード払、口座振替、コンビニ払など
- 請求方法:窓口精算(動物病院の窓口で精算)、診療後に郵送で保険金請求、WEBから簡単に保険金請求
- 付帯サービス:24時間電話相談サービスや獣医師によるヘルスケア相談サービス
ペット保険比較サイト「i保険」では、各商品の補償割合や保険料をわかりやすく比較できる、ペット保険人気ランキングやプラン別に詳細を一括比較できる保険料検索ページがあります。対象のペットの種類に合わせてぜひご活用ください。
まとめ:告知義務を理解したうえで安心のペット保険加入を
ペット保険の告知義務は、いざという時に適切な補償を受けるために欠かせない大切なルールです。虚偽の申告は「バレないだろう」という甘い考えで済むものではなく、保険金が支払われない、契約が解除される、他社でも加入を断られるリスクを招きます。
だからこそ、ペットの健康状態を正直に伝え、告知義務をきちんと果たした上で、自分のペットに合った補償内容や保険料をしっかり比較し、納得してペット保険を選ぶことが大切です。
大切な家族であるペットが安心して治療を受けられるように、トラブルを防ぎ、いざという時に本当に役立つ保険に加入しておきましょう。
この記事では一般的なペット保険で多いケースを紹介しています。実際の保険内容は各保険会社の最新の約款をご確認ください。
- 執筆者
- 染谷 弥幸(1級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
「安心できる金融商品選びをわかりやすくカンタンに」という当社のミッションを胸に、お客様が自分に合った商品をみつけるための情報をわかりやすく紹介します。