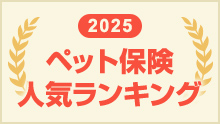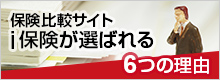ペット保険お役立ち情報
ペット保険の免責事項とは?
補償外になる主なケースを解説

更新日:
ペット保険への加入を検討している飼い主さんの中には、「どんな場合でも補償してもらえるの?」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。実は、ペット保険には「免責事項(免責事由)」と呼ばれる、補償の対象外となるケースがあらかじめ定められています。
加入後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためにも、事前に免責事項について正しく理解しておくことが大切です。
この記事では、ペット保険の主な免責事項について具体的な事例とともに解説し、加入前に知っておくべきポイントをお伝えします。免責事項があっても、ペット保険は多くのメリットがある重要な備えです。正しい知識を身につけて、大切な家族であるペットを守るためにも最適な保険選びをしましょう。
- 保険会社によって「免責事項」という表現ではなく、「補償対象外となるケース」「給付されない場合」などと表記されていることもあります。
- 目次
補償されない主なケースとは?
免責事項を事例で解説
ペット保険には、どの保険会社でも補償の対象外となるケース、いわゆる「免責事項(免責事由)」が存在します。ここでは、ペット保険で補償されない主なケースを4つのカテゴリーに分けて、具体例とともに解説します。
- 一部の保険会社はこちらで紹介する、補償対象外の例も補償対象としている場合があります。詳細は各社の商品ページよりご確認ください。
予防・健康管理に関する補償対象外の例
病気の予防や健康維持のための処置は、一般的に補償対象外とされています。
ワクチン接種
混合ワクチンや狂犬病予防注射などの予防接種費用は補償されません。これらは病気の予防が目的であり、治療ではないためです。
- ワクチン接種後の副作用による治療は補償されることがあります。保険会社の約款を確認しましょう。
健康診断
定期的な健康チェックや血液検査などの健康診断費用も対象外です。病気の早期発見には重要ですが、予防的な側面が強いため保険適用外となります。
フィラリア予防薬
フィラリア症の予防薬や定期的な検査費用は補償されません。これも予防医療の範囲に含まれるためです。
繁殖・美容に関する補償対象外の例
繁殖や美容目的の処置についても補償対象外となります。
去勢・避妊手術
病気治療以外の目的で行われる去勢手術や避妊手術は補償されません。
- ただし、子宮蓄膿症や精巣腫瘍などの病気治療として行われる場合は補償される可能性があります。保険会社の約款を確認しましょう。
妊娠・出産関連費用
正常な妊娠・出産に関わる費用は補償対象外です。帝王切開が必要になった場合でも、異常分娩として医学的に必要と認められない限り補償されないケースが多いです。
美容目的の処置
トリミング、爪切り、耳掃除、歯石除去(予防目的)、断尾・断耳などの美容や外見を整える目的の処置は補償されません。
既往症・先天性疾患の補償対象外の例
保険加入前から存在していた病気や生まれつきの疾患も補償されないのが一般的です。
既往症
保険加入前に既に発症していた病気や、その病気に関連する治療費は補償されません。例えば、保険加入前に皮膚炎を発症していた場合、加入後の皮膚炎治療は補償対象外となります。
先天性疾患
その他の補償対象外の例
先述した例の他にも、様々な免責事項が設定されています。
自然災害による怪我
地震、津波、噴火などの天災による怪我や病気は補償されないことが一般的です。
飼い主の故意・重過失
飼い主が故意に怪我をさせた場合や、重大な過失により生じた怪我は補償対象外です。
代替療法・民間療法
鍼灸、マッサージ、アロマテラピーなどの代替医療は、獣医師による正当な治療と認められない場合、補償されないことがあります。
薬事法に違反する治療
未承認の薬剤を使用した治療や、薬事法に違反する治療行為は補償対象外となります。
- 特約で補償範囲が広がるケースもあるため、詳細は各社の補償内容を確認することが重要です。
そもそも「免責事項」とは?
知らないと損する基本知識
免責事項の基本的な定義
免責事項とは、保険会社が保険金の支払い責任を負わない事由を定めたものです。言い換えれば、「この条件に該当する場合は保険金をお支払いしません」という約束事です。
ペット保険における免責事項は、保険約款に詳細に記載されており、契約者はこれに同意した上で保険に加入することになります。
保険会社によっては、約款の中で「免責事項」という言葉を明示的に使用せず、「保険金をお支払いできない場合」や「補償対象外となる事由」といった表現を用いていることがあります。
これは、ペット保険に加入する方にとって内容がわかりやすくなるよう、より具体的な記載を意図しているためです。ただし、これらは一般的に「免責事項」としてまとめて理解されており、実質的には保険会社が補償の対象外とする条件を示しています。
なぜ免責事項が設定されているのか
免責事項が設定される理由は主に3つあります。
- 保険制度の健全な運営
- もしすべての医療費を無制限に補償すれば、保険料が非常に高額になってしまいます。合理的な保険料設定のために、一定の制限が必要です。
- モラルハザード
(保険に甘えてリスク管理が甘くなる行動)の防止 - 保険があることで、ペットの飼い主が過度に無責任な行動を取ることを防ぐ目的もあります。予防医療を保険対象にしないのは、飼い主自身のペットへの健康管理の責任を促すためでもあります。
- 保険の本来の目的の明確化
- ペット保険の主目的は、予期しない病気や怪我による高額な治療費負担を軽減することです。予防や美容など、計画的に行えるものは対象外とすることで、保険の役割を明確にしています。
保険約款での確認ポイント
保険約款を確認する際は、以下のポイントに注意しましょう。
免責事項の記載場所
多くの場合、約款の「保険金をお支払いしない場合」や「免責事項」という章に詳細が記載されています。
具体的な事例の確認
抽象的な表現だけでなく、具体的な病名や処置名が記載されているかを確認しましょう。
例外規定の有無
一般的には対象外でも、特定の条件下では補償される場合があります。これらの例外規定も見逃さないよう注意が必要です。
加入前に必読!免責事項を見落とすと起こりがちな問題
ペット保険に加入する際、免責事項をよく確認せずに手続きを進めると、「保険が使えると思っていたのに使えなかった」といったトラブルが発生することがあります。ここでは、免責事項を理解せずに加入してしまった場合に起こりうる4つのリスクを具体的に解説します。
期待していた保険金が受け取れない
最も深刻なのは、治療費の支払いの負担を保険金でカバーできると期待していたにも関わらず、免責事項に該当するため保険金が支払われないケースです。高額な治療費を全額自己負担することになり、経済的な負担が重くのしかかってしまいます。
例えば、愛犬が椎間板ヘルニアになり手術費用30万円がかかった場合、「保険に入っているから大丈夫」と思っていたら、保険加入前から治療をしていたため既往症として免責事項に該当し、全額自己負担になってしまうことがあります。高額な治療費を突然支払うことになり、経済的な負担だけでなく「保険に入っていたのに意味がなかった」という精神的なショックも大きくなります。
補償されると思っていた治療が対象外?保険会社との認識ズレに注意
加入者が「補償対象のはず」と思っていた治療が、保険会社では「免責事項に該当する」と判断されることがあります。
例えば、契約者がペットの健康診断費用も補償対象と考えていても、保険会社は「予防・健康管理目的」と判断し、補償対象外となる可能性が高いです。このような認識の相違は、保険金請求時のトラブルの原因となり、飼い主さんの不満や不信につながります。
ペットに合っていない保険に加入して損をする可能性も…
自分のペットにとって必要となる可能性が高い治療が免責事項に含まれている場合、その保険への加入が本当に適切かどうか、慎重に検討する必要があります。
例えば、顎の骨が小さく歯が密集している小型犬などは歯周病になりやすい傾向にありますが、その治療が補償対象外だとわかっていれば、そもそも別の保険で補償対象になっているものがないかなどを選ぶ判断ができます。
このように免責事項を確認せずに契約すると、実際に必要になる治療がカバーされていないことに後で気づき、保険料を払っていても「使いたいときに使えない保険」になってしまうリスクがあります。
必要な費用に備える対策ができない
免責事項を知らないことで、本来なら別の手段で備えるべき費用について準備ができていない状態になります。
例えば、ワクチン接種の費用などが免責事項になることを知らずにいると、「保険があるから大丈夫」と思い、これらの予防医療費を別途貯蓄で備えることを怠ってしまう可能性があります。
このように免責事項を把握していないと、ペット保険とは別に予防医療や定期健診、トリミングなどのために貯蓄での備えが不十分になってしまいます。
- CHECK
-
「保険に入っているから大丈夫」と思っていても、免責事項を知らないままペット保険に加入すると、使えると思ったときに使えない可能性があります。このようなことがないように、加入前に約款をしっかり確認し、ご自身のペットに合った補償内容かどうかを見極めることが大切です。
補償されないケースがあってもペット保険は必要な理由
免責事項があることを理解した上でも、ペット保険への加入は多くの飼い主さんにとって有益です。
ペットの病気・怪我の治療費は高額になりがち
動物の医療費には人間のような公的保険制度がないため、治療費は全額自己負担となります。
手術を受ける場合、骨折手術で約20万円、腫瘍摘出手術で10万円〜30万円など、一度の手術で高額な費用がかかることは珍しくありません。
さらに慢性疾患など定期治療が必要な場合、月数万円の治療費が長期間続くことがあります。糖尿病のインスリン治療では月2万円〜3万円、腎臓病の継続治療でも月1万円〜2万円程度かかることがあります。
加えて、夜間や休日の緊急診療を受けた場合、通常の診療費に加えて時間外料金がかかり、より高額になる傾向があります。
経済的負担の軽減効果
ペット保険の最大のメリットは、高額な治療費の経済的負担を軽減できることです。
加入した保険の補償割合により自己負担額を軽減することができます。例えば、70%補償のプランなら、10万円の治療費のうち7万円が保険でカバーされ、自己負担は3万円に軽減されます。
加入するペット保険の補償割合に応じて、補償される保険金の金額は異なります。各社の補償割合ついての詳細は「ペット保険で補償される割合は?各社の補償割合一覧」をご確認ください。
ペット保険は年間で1回の手術や通院・入院に支払限度額や日数を設けている商品が多いです。ただし、よほど高額な治療が続かない限り、設定されている支払限度額以内で大部分の費用をペット保険でカバーできます。
ペット保険比較サイト「i保険」では、各商品の補償割合や、通院・入院・手術の限度額をわかりやすく比較できる、ペット保険人気ランキングやプラン別に詳細を一括比較できる保険料検索ページがあります。対象のペットの種類に合わせてぜひご活用ください。
安心して治療を受けられる精神的メリット
経済的な負担軽減だけでなく、精神的な安心感もペット保険加入の重要なメリットです。
治療選択肢の拡大
高額な治療でも、保険があることで躊躇なく決断できます。費用を気にすることなく、ペットにとって最適な治療を選択できるため、「お金がないから治療を諦める」という辛い選択をする必要がなくなります。
例えば、手術が必要な場合でも、経済的な理由で内服治療に留めるのではなく、根本的な治療を選択できます。
早期治療への後押し
「様子を見る」のではなく、気になる症状があればすぐに病院に連れて行けます。早期発見・早期治療により、結果的に治療費を抑えられる場合も多く、ペットの負担も軽減できます。
ペット保険があることで、軽微な症状でも気軽に受診できる安心感は非常に大きなメリットです。
予防サポートも!嬉しい付帯サービス
ペット保険には、加入者向けのサービスとして、定期的な健康チェックの割引や、健康相談窓口の提供など、予防医療をサポートするサービスなどが用意されている商品があります。
例えば、病気の早期発見に役立つ健康チェックが受けられたり、獣医師への無料電話相談が利用できるケースなどがあります。これらは補償対象外となる予防医療に対して、間接的に飼い主をサポートしてくれるサービスです。
こうしたサービスを活用することで、病気の早期発見や生活習慣の改善につながり、結果的に医療費の削減やペットの健康寿命を延ばすことに役立つ可能性があります。
家計への影響軽減
突発的な高額治療費で家計が圧迫されることがないため、家族全体の生活の安定につながります。
急な出費に慌てることなく、冷静に治療方針を決められる環境は、飼い主さんとペット双方にとって非常に価値のあるものです。
- CHECK
-
これらのメリットは、免責事項による一部の制限を考慮しても、十分に価値のあるものです。
免責事項をふまえたペット保険を選ぶ際の注意点と比較のコツ
免責事項について理解したうえで、どのようにペット保険を選べばよいのでしょうか。保険選びの際の重要なポイントをご紹介します。
保険会社・プランの比較ポイント
POINT1:免責事項の範囲を比較する
保険会社によって免責事項の範囲は異なります。特に以下の点について比較検討しましょう。
- 既往症の取り扱い方針
- 遺伝性疾患の補償範囲
- 高齢時の制限事項
- 慢性疾患の継続補償
POINT2:補償内容と保険料のバランスをみる
単純に保険料の安さだけでなく、補償内容とのバランスを総合的に判断することが重要です。
- 補償割合(50%、70%、90%、100%など)
- 年間補償限度額
- 1日あたりの補償限度額
- 年間利用回数制限
POINT3:付帯サービスや便利なシステムの充実度
保険金支払い以外の保険会社による付帯サービスや、便利なシステムも比較のポイントとなります。
- 24時間電話相談サービス
- 獣医師によるヘルスケア相談
- 優待サービス
- 窓口精算
- WEBで簡単に保険金請求
加入タイミングの重要性
ペット保険は早期加入がメリットが大きいとされています。その理由は以下の通りです。
- 早期加入のメリット
-
- 既往症が少ない状態で加入できる
- 年齢制限に引っかかる前に加入できる
- 保険料が安い年齢から開始できる
- 待機期間を早めにクリアできる
このように、早期に加入することでさまざまな条件をクリアでき、将来にわたって安心してペットと暮らすことができます。
加入タイミングの目安は、ワクチン接種後の生後2~3か月が理想的です。7歳未満であれば、年齢による制限がなく、幅広い選択肢からペット保険を選べる可能性が高くなります。7歳以上になると選択できるペット保険の種類が絞られてくるので、ペットを家族に迎える方は早めにペット保険の比較検討することをおすすめします。
ペット保険比較サイト「i保険」では、ペットの年齢を選択してプラン別に詳細を一括比較できる「保険料検索ページ」があります。年齢制限がご心配な方はぜひご利用ください。
選択肢が絞られる高齢のペットでも申込みできる保険は存在します。高齢のペットが新規申込みできる保険をお探しの方は、「ペット保険は何歳まで入れる?シニアの犬・猫・鳥・うさぎも加入できる保険」も参考にしてください。
まとめ:免責事項を理解して、後悔しない保険選びを
ペット保険には、補償対象外となる「免責事項」が設定されています。ペット保険の免責事項は、加入前に必ずチェックすべき重要な要素です。予防処置や既往症、美容目的の治療などは保険金の対象外となるケースが多いため、事前にしっかり確認することが大切です。
「補償されないこと」を正しく理解し、必要な補償が受けられる保険を比較・検討することで、後悔のない保険選びが可能になります。大切な家族であるペットの未来を守るために、正しい情報と知識をもって備えておきましょう。
この記事では一般的なペット保険に多いケースを紹介しています。また、診療費は動物病院や地域によって異なります。実際の保険内容は各保険会社の最新の約款をご確認ください。
- 執筆者
- 染谷 弥幸(1級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
「安心できる金融商品選びをわかりやすくカンタンに」という当社のミッションを胸に、お客様が自分に合った商品をみつけるための情報をわかりやすく紹介します。