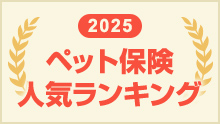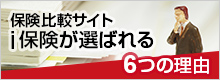ペット保険お役立ち情報
ペット保険の複数加入とは?
2つ入るメリット・デメリット

更新日:
大切な家族であるペットの医療費に備えるペット保険ですが、1匹のペットに対して複数の保険に加入する「複数加入」や「掛け持ち」が可能なことをご存知でしょうか。現在のペット保険では補償が物足りないと感じている方や、より手厚い補償を求める方に注目されている加入方法です。
この記事では、ペット保険の複数加入の仕組みから、メリット・デメリット、目的別の組み合わせ方の例など詳しく解説します。
- 目次
ペット保険の複数加入とは?基本的な仕組みと多頭割引との違い
「今のペット保険だけでは不安…」「2つ入っても大丈夫?」そんな疑問を持つ方のために、ペット保険の複数加入について、基本的な仕組みや多頭飼い割引との違い、検討すべきケースをわかりやすく解説します。
1匹のペットに2つ以上保険をかける場合
ペット保険の複数加入とは、同じペット1匹に対して2つ以上のペット保険に同時に加入することを指します。一般的には「掛け持ち」や「重複加入」、「併用」などとも呼ばれ、多くの保険会社で認められている加入方法です。
複数加入することで、それぞれの保険の特長を活かした組み合わせが可能になり、単独加入では得られない手厚い補償を実現できます。ただし、保険会社によっては重複加入を不可としている場合もあります。また、多くの保険会社では事前の告知が必要で、これに違反すると契約できたとしても契約解除になる可能性もあるので、申告漏れのないように気をつけましょう。
告知義務についての詳細は、「ペット保険の告知義務とは?「バレない」は危険!申告の注意点」をご確認ください。
多頭飼い割引との違いを明確にしよう
複数加入と混同しやすいのが「多頭飼い割引」ですが、これらは全く異なる仕組みです。
複数加入と多頭飼い割引の違いを比較
| 複数加入 (1匹に2つの保険) |
多頭飼い割引 |
|---|---|
| 1匹のペットに対して 複数の保険に加入 |
同一契約者が複数のペットを同じ保険会社で契約 |
| 補償内容を 手厚くすることが目的 |
保険料の 割引を受けることが目的 |
| 保険料は加入した 保険分だけ発生 |
保険料が2~3%割引 |
多頭飼い割引について詳しく知りたい方は、「犬・猫の多頭飼いに必要な知識を解説!多頭割引のペット保険も比較」をご覧ください。
どんなケースで複数加入を検討するのか
ペット保険の複数加入を検討するのはどのような場合でしょうか。
こちらでは主なケースを紹介します。
CASE1:補償内容に不満がある場合
「思ったより保険がきかない」「もっと補償してくれるプランにすればよかった」など感じた場合です。現在加入している保険の補償割合が低い、年間限度額が少ないなど、補償内容に物足りなさを感じたときは、もう一つ保険を追加することで不足を補う選択肢もあります。
CASE2:特定のリスクに備えたい場合
「手術費用が高いと聞いて不安…」など、現在の保険だけではカバーしきれない治療が心配な場合です。手術費用だけを手厚くしたい、通院補償も追加したいなど、特定の治療に備える意図で検討されます。
このようなときは、必要な部分をカバーする保険を追加することで、補償内容を充実させられます。
CASE3:保険会社のリスク分散をしたい場合
「もし加入している保険会社の商品が販売停止になったら…」など、1社だけでは不安で、複数の保険会社に分散してリスクを軽減したい場合です。 万が一の備えとして、信頼性のある複数社を併用する選択も一つの手です。
ペット保険を2つ以上加入することで得られる4つのメリット
ペット保険を2つ以上加入することで得られるメリットは多岐にわたります。ここでは主なメリットを4つご紹介します。
メリット 1補償や限度額の不足を補える
現在の保険でカバーできない部分を、もう1つの保険で補えるのが大きなメリットです。例えば、入院・手術のみ補償される保険に、通院補償が含まれる保険を組み合わせることで、通院・入院・手術のフルカバーの補償を実現できます。
また、年間限度額や1日あたりの支払上限がある場合でも、2社に加入していれば、結果的に補償金額を実質的に増やせる可能性があります。例えば、年間50万円まで補償される保険を2社利用すれば、最大100万円まで補償を受けられることもあります。
ただし、ペット保険は「実損払い」が基本で、実際にかかった費用以上の保険金は受け取れません。あくまで補償の選択肢を広げる手段として考えることが大切です。
メリット 2保険会社のリスク分散効果
1つの保険会社だけに依存するリスクを分散できます。保険会社の経営状況の変化や、保険金支払いに関する解釈の違いなど、会社固有のリスクを軽減できる効果があります。
複数の保険会社に分散することで、より安定して保険の補償を受けられる可能性が高まります。
メリット 3異なる特色のサービスを組み合わせ可能
保険会社によって、補償の特色や商品の付帯サービスや付帯できる特約など得意分野が異なります。
保険会社の特色の違いの例
| A社 | 通院・入院・手術などの 日数や回数制限がない |
|---|---|
| B社 | 飼い主さんに万一のことがあった場合に、 ペットが継続して飼育されるように 飼育費用補償保険金がある |
| C社 | 24時間獣医師相談や窓口精算など 付帯サービスが充実している |
- ポイント
- このように、それぞれの強みを組み合わせることで、単独加入では実現しにくい手厚い補償やサービスを受けられる可能性があります。
メリット 4段階的な保険見直しが可能
複数加入していることで、将来的な保険の見直しを段階的に行えます。一度に2つの保険を変更するのではなく、1つずつ検討・変更することで、リスクを抑えながら最新の商品への乗り換えや、より良い保険構成の実現につなげることができます。
ペット保険を複数加入することで生じる3つのデメリット
複数加入には多くのメリットがありますが、一方で注意しておきたいデメリットもあります。検討する際は、両面から冷静に判断することが大切です。
デメリット 1保険料負担が2社分に増加
まず考慮すべきデメリットのひとつが保険料の増加です。保険の数に応じて保険料が発生するため、支払いが増えてしまう点には注意が必要です。
複数加入を検討する際は、増加する保険料と得られる補償の充実度を慎重に比較検討する必要があります。保険料の合計が高額になりすぎて家計に無理が生じる場合は、加入の見直しも検討しましょう。
デメリット 2保険金請求や契約管理が複雑化
複数の保険に加入することで、保険金請求や契約の管理が複雑になります。
- 保険金請求手続き
-
- 複数の保険会社への請求手続きが必要
- 各社で異なる請求書類の準備が必要
- 請求時期や請求方法の違いの理解が必要
- 契約管理
-
- 複数の契約内容の把握
- 更新時期の把握
- 保険料支払いの管理
治療が頻繁になると、請求業務の負担が大きくなる可能性があります。特にペットが高齢になってくると、治療をして保険金請求をする割合が増えるので、事前に手続きや管理の手間が増えることを理解しておくことが大切です。
また、2つの保険会社に加入する場合は、それぞれの保険会社で、異なる契約手続きを個別に行う必要があります。そのため1社の契約手続きよりも2社に増えた分、手続きにかかる時間は増えるといえるでしょう。
デメリット 3重複補償により受け取れる保険金の制限を理解する必要
ペット保険は原則実損払いのため、実際にかかった治療費を超えて保険金を受け取ることはできません。また、複数の保険から保険金を受け取る場合は「按分払い(あんぶんばらい)」という仕組みが適用されることがあります。
これらの仕組みを正しく理解していないと、2社それぞれから期待していた保険金を受け取れない可能性もあるため、制度の仕組みを理解しておくことが大切です。こうした重複補償の仕組みについては、次の章「重複補償の仕組みと請求時の注意点」で詳しくご紹介します。
重複補償の仕組みと請求時の注意点
複数加入の際に最も気をつけなければいけない注意点でもある、「重複補償の仕組み」について、具体例を交えて詳しく解説します。
按分払い(あんぶんばらい)の仕組み
複数のペット保険に加入している場合、実際の治療費に対して各保険会社がどのように保険金を支払うかは「按分払い」という仕組みで決まります。按分払いとは簡単にいうと、それぞれの保険会社が治療費を分担して支払う方式のことです。
以下は、按分払いがどのように計算されるかを示した具体的な例です。
実際に支払った治療費が10万円だった場合の
按分払いの計算例
| 項目 | A社保険 | B社保険 |
|---|---|---|
| 補償割合 | 70% | 50% |
| 単独での 保険金 |
7万円 | 5万円 |
| 合計 保険金 |
12万円(治療費10万円を超過) | |
| 按分 計算後の 支払額 |
10万円 × 7万円 ÷ 12万円 = 約5.8万円 |
10万円 × 5万円 ÷ 12万円 = 約4.2万円 |
| 合計 支払額 |
10万円(按分計算され治療費と 同額の保険金が受け取れる) |
|
このように、保険金総額が治療費を上回る場合、実際には「各保険会社が分担して実費を上限に支払う」形となります。単独の保険ごとに計算した保険金をそれぞれの会社から受け取れるわけではないので、この点を誤認しないように注意しましょう。
複数加入の場合の保険金請求時の注意点
ペット保険を複数契約している場合、保険金請求には単独加入と異なる注意点があります。よくあるトラブル例をご紹介します。
- よくあるトラブル例
-
保険加入時に他社保険にも加入している申告を忘れてしまった
告知義務違反と見なされ、保険金が支払われなかった。
-
按分払いの仕組みをよく理解していなかった
「2社でそれぞれの補償割合分の保険金がもらえると思っていた」などの誤解しており、実際に受け取れた保険金が、想定していたよりも少なく戸惑った。
-
保険会社同士の連携に時間がかかる
情報照会に時間を要し、支払いが遅延したケースも。
これらのトラブルを避けるためには、加入時の正確な告知と、仕組みの正しい理解が不可欠です。特に、請求時には『どの保険にどれだけ請求できるか』の目安を事前に保険会社に確認しておくことをおすすめします。複数加入を検討している段階で、保険会社のカスタマーサポートに相談するのも一つの手です。
各社のお問合せ先は「保険会社からペット保険を選ぶ」の保険会社一覧ページより各社のお見積りボタンを押下してご確認ください。
目的別に選ぶ!複数加入の組み合わせ3例と選ぶポイント
実際に複数加入を検討する際の補償内容や家計のバランスを考慮した、代表的な複数加入の組み合わせパターンを紹介します。「どんな人に向いているか」「どう役立つか」もあわせてご確認ください。
ご紹介している内容は一般的なケースを元にしたもので、実際のご契約内容によって異なります。詳細は各保険会社の約款や商品内容をご確認ください。 また、複数のペット保険に加入している場合でも、実際にかかった治療費を超えて保険金が支払われることはありません。 保険金の支払いは実際の治療費を上限として、各保険会社の定める補償内容に基づいて行われます。
パターン1:フルカバー型+手術特化型
(手術費用の手厚い備え)
▶ 「とにかく手術が高額で不安…」という方におすすめの組み合わせ
- 1社目の契約:
フルカバー型 -
- 通院・入院・手術
50%補償 - 年間限度額
50万円
- 通院・入院・手術
- 2社目の契約:
手術特化型 -
- 手術
70%補償 - 年間限度額
30万円
- 手術
2つの保険を組み合わせで実現できる補償
- 手術 ………… 実質100%に近い補償が受けられる
- 通院・入院 … 1社目の契約の保険で50%補償
- 年間限度額 … 最大80万円に拡大
1社目の契約で日常的な治療をカバーしつつ、高額になりがちな手術には特化型プランを追加する組み合わせです。手術特化型は保険料が比較的安いため、コストを抑えながら手術への備えを強化できます。
- このパターンのメリット
-
- 手術費用の自己負担を大幅に軽減できる
- 追加保険料を抑えながら手術補償を充実
- 通院治療も含めた幅広い補償を維持
パターン2:入院・手術特化型+フルカバー型(通院補償のカバー)
▶ 「通院補償がない保険に加入したがやっぱり通院にも備えたい…」というケースにおすすめ
- 1社目の契約:
入院・手術特化型 -
- 入院・手術のみ
70%補償 - 年間限度額
70万円
- 入院・手術のみ
- 2社目の契約:
フルカバー型 -
- 通院・入院・手術
50%補償 - 年間限度額
60万円
- 通院・入院・手術
2つの保険を組み合わせで実現できる補償
- 入院・手術 … 実質100%に近い補償が受けられる
- 通院 ………… 2社目の契約の保険で50%補償
- 年間限度額 … 最大130万円に拡大
入院・手術に特化した1社目の契約に、通院補償も含むフルカバー型を追加する組み合わせです。既に手厚い入院・手術補償を持ちながら、不足している通院補償を補完できます。
- このパターンのメリット
-
- 不足していた通院補償を追加で確保
- 高額な入院・手術費用の自己負担を軽減
- 年間限度額の増額で長期治療にも対応
パターン3:フルカバー型+フルカバー型
(補償割合50%を2つ掛け持ちで実質100%補償)
▶ 「補償割合50%にしてみたけど自己負担を減らしたい…」という方におすすめの組み合わせ
- 1社目の契約:
フルカバー型 -
- 通院・入院・手術
50%補償 - 年間限度額
50万円
- 通院・入院・手術
- 2社目の契約:
フルカバー型 -
- 通院・入院・手術
50%補償 - 年間限度額
100万円
- 通院・入院・手術
2つの保険を組み合わせで実現できる補償
- 通院・入院・手術 … 実質100%に近い補償が受けられる
- 年間限度額 … 最大150万円に拡大
同じ補償割合の保険を2つ組み合わせることで、按分計算後も治療費の全額補償を実現するパターンです。自己負担をほぼゼロにしたい方におすすめの組み合わせです。
- このパターンのメリット
-
- 通院・入院・手術すべてで自己負担がほぼゼロ
- 両方フルカバー型なので補償対象の治療ならどんな治療にも対応可能
- 年間限度額が大幅に増額され長期治療も安心
組み合わせを選ぶ際の重要ポイント
1.まずは「足りないと不安な部分はどこか」目的を明確にする
手術・通院・入院など、心配なシーンはどこか?備えたい場面を明確にしましょう。それによって、組み合わせる保険の方向性が大きく変わってきます。
2.保険料とのバランスをしっかりチェック
複数加入により保険料は、その分増加します。月々の保険料が家計を圧迫しないよう、無理のない範囲で設定することが重要です。
3.保険会社の組み合わせを検討
異なる保険会社を選ぶことで、サービスの多様性とリスク分散効果を得られます。ただし、請求手続きが複雑になることも考慮して選択しましょう。
4.将来の見直しやすさ
ペットの年齢や健康状態は変化します。将来的にプランを調整しやすい組み合わせを選ぶことで、長期的に最適な保険構成を維持できます。
複数加入以外の選択肢も検討しよう
複数加入を検討する前に、他の選択肢でも目的を達成できないか確認することが大切です。
プラン変更での対応
複数加入を検討する前に、現在加入している保険のプラン変更で対応できないか確認してみましょう。手厚いプランへ変更できる場合があります。変更の手続きや制限などは保険会社によって異なります。
- プラン変更のメリット
-
- 契約する保険会社が増えないので、管理が簡単(1つの契約のみ)
- 1社への請求なので請求手続きが複雑化しない
- 2つの保険に加入するより、保険料の増加を抑えられる可能性
乗り換えという選択肢
現在の保険に不満がある場合は、より条件の良い他社への乗り換えも選択肢の一つです。
最新の状況や飼い主さんのニーズに合わせて、より良い条件の商品が新たに他社から販売される可能性もあります。
ペット保険の乗り換えについて詳しく知りたい方は、「ペット保険の乗り換え方法とは?注意点・ベストタイミングを解説」をご参照ください。
まとめ|複数加入は「目的」と「バランス」を重視して判断
ペット保険の複数加入は、単独加入では得られない手厚い補償を実現できる有効な手段です。しかし、保険料の増加や管理の複雑化というデメリットもあります。
複数加入を検討する際は、まず「なぜ複数加入したいのか」という目的を明確にすることが重要です。手術費用への不安なのか、通院補償の追加なのか、それとも年間限度額の不足なのか。目的が明確になれば、最適な組み合わせも見えてきます。
また、保険料と補償内容のバランスも慎重に検討しましょう。複数加入により保険料は確実に増加しますが、その分得られる安心感や補償の充実度と見合っているかを冷静に判断することが大切です。プラン変更や乗り換えといった他の選択肢も含めて比較検討し、あなたとペットにとって最適な保険構成を見つけてください。
この記事では一般的なペット保険に多いケースを紹介しています。実際の保険内容は各保険会社の最新の約款をご確認ください。
- 執筆者
- 染谷 弥幸(1級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
「安心できる金融商品選びをわかりやすくカンタンに」という当社のミッションを胸に、お客様が自分に合った商品をみつけるための情報をわかりやすく紹介します。