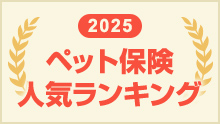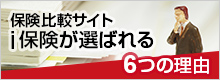ペット保険お役立ち情報
ペットの防災対策完全ガイド!
災害に備えた準備・避難所での注意点

更新日:
近年、地震や台風、洪水などの自然災害が頻発する中、私たち人間だけでなく、大切な家族の一員であるペットの防災対策も欠かせません。災害時にペットと一緒に安全に避難し、避難生活を送るためには、日頃からしっかりとした準備が必要です。
この記事では、ペットの防災対策について、事前の準備から災害発生時の対応、避難所での注意点まで、愛犬・愛猫などのペットを守るために知っておきたい情報をわかりやすくお伝えします。
- 目次
ペットの防災対策の重要性
災害はいつ発生するかわからず、ペットも私たちと同様に被災者となります。ペットの命を守り、災害時の混乱を最小限に抑えるためには、飼い主としての責任を理解し、適切な準備を行うことが重要です。
災害がペットにもたらす影響
災害時、急激な環境の変化、大きな音や揺れ、普段と異なる匂いなどにより、ペットは極度の不安状態に陥る可能性があります。また、災害による影響は以下のようなものが考えられます。
- 身体的な影響
- ケガや病気、
栄養不足、
脱水症状など
- 精神的な影響
- パニック状態、
食欲不振、
無気力状態など
- 行動的な影響
- 普段とは異なる行動、
攻撃的になる、
隠れて出てこないなど
これらの影響を最小限に抑えるためには、事前の準備と適切な対応が不可欠です。
飼い主の責任と準備の必要性
ペットを飼うということは、災害時においても最後まで責任を持って世話をするということです。ペットは自分で避難することも、食料を確保することもできません。すべて飼い主さんの判断と行動にかかっています。
災害時にペットと一緒に避難する「同行避難」は、多くの自治体で推奨されていますが、避難所でのペット受け入れには制限がある場合も多く、事前の準備なしでは困難な状況に直面する可能性があります。
過去の災害から学ぶ教訓
東日本大震災などの過去の災害では、多くのペットが被災し、飼い主と離ればなれになったり、避難所での生活に適応できずに体調を崩したりするケースが数多く報告されました。
環境省の「東日本大震災における被災動物対応記録集」によると、確認されているだけでも青森県で31頭、岩手県で602頭、福島県では約2,500頭の犬が死亡したとされています。その他にも、命は助かったものの負傷したり、避難する際に飼い主と離ればなれとなり、放浪状態となったペットが多数あったことが分かっています。
これらの教訓から、事前の備えがいかに重要かがわかります。災害が発生してから慌てて準備するのではなく、普段からペットの防災対策を講じておくことが、ペットの命を守ることにつながります。
ペットの災害に備えた事前準備
災害時にペットの安全を確保するためには、日頃からの準備が欠かせません。防災グッズの準備、しつけ、健康管理など、総合的な準備を行いましょう。
CHECK 1ペット用防災グッズの準備リスト
ペット用の防災グッズは、最低でも3日分、できれば1週間分を目安に準備しましょう。以下は、準備しておきたい防災グッズのチェックリストです。
- 基本的な生活用品
-
- フード(普段食べているもの):7日分
- 飲料水:7日分
- 食器(軽くて割れにくい材質)
- リードやハーネス(予備を含む)
- 首輪(迷子札付き)
- ケージやキャリー
- ペットシーツやトイレ用品
- タオルや毛布
- 健康・医療用品
-
- 常備薬(処方薬がある場合)
- 応急処置用品
- 消毒液
- 包帯やガーゼ
- その他の必需品
-
- ペットの写真(迷子対策)
- 飼い主の連絡先を記載したメモ
- ワクチン接種証明書
- ビニール袋(排泄物処理用)
- おもちゃ(ストレス軽減のため)
- ウェットティッシュ
- ペット用防災グッズ準備のポイント
- これらのグッズは、定期的に点検し、賞味期限が切れる前に交換することを心がけましょう。
CHECK 2災害に備えたペットのしつけと健康管理
災害時にペットが適切に行動できるよう、普段からのしつけと健康管理が重要です。
災害に備えた基本的なしつけ
災害時に最も重要なのは、飼い主の指示に従って行動できることです。以下のしつけを日頃から行いましょう。
- 基本的なしつけ
-
- 「待て」「おいで」などの基本コマンドの徹底
- リードでの歩行訓練
- 他の人や動物との適切な接し方
- 無駄吠えの抑制
特に、避難所では多くの人や動物が共同生活を送るため、他者に迷惑をかけないよう、基本的なマナーを身につけておくことが大切です。
ケージ・キャリーの準備と慣らし訓練
災害時の避難や避難所での生活では、ケージやキャリーでの生活が必要になります。普段からケージやキャリーに慣れさせておくことで、災害時のストレスを軽減できます。
- ケージ・キャリーの慣らし訓練
-
- 普段からケージを生活空間の一部として使用
- ケージの中で食事をする習慣をつける
- 短時間から始めて、徐々に長時間過ごせるよう訓練
- 車での移動にも慣れさせる
感染症対策(ワクチン・予防)
避難所では多くの動物が集まるため、感染症のリスクが高まります。定期的なワクチン接種や予防対策をして、ペットの健康を守りましょう。
- 接種すると良いワクチンの種類
-
- 混合ワクチンの接種
- 狂犬病ワクチンの接種(犬は年1回の接種が法的義務。猫は対象外)
- 予防が必要な感染症対策
-
- フィラリア予防(内服薬・注射など)
- ノミ・ダニ予防(スポット薬・内服薬など)
- フィラリア・ノミダニの予防は通年または季節に応じて、獣医師の指示に従う
ワクチン接種の記録は、避難所での受け入れ条件となる場合があるため、証明書を防災グッズと一緒に保管しておきましょう。
CHECK 3災害時に役立つマイクロチップ・迷子札の重要性
災害時に飼い主とペットが離ればなれになってしまうケースは少なくありません。万が一の場合に備えて、身元確認ができるよう準備しておくことが重要です。
マイクロチップの装着

マイクロチップは、ペットの皮下に埋め込む小さなチップで、専用のリーダーで読み取ることで飼い主の情報を確認できます。マイクロチップの利点は、偽造や改ざんが困難で半永久的に使用でき、災害の混乱時など首輪が外れても身元確認が可能なことです。
迷子札の装着

マイクロチップと併用して、首輪に迷子札を装着することも重要です。迷子札なら専用機器がなくても、すぐに飼い主の連絡先を確認できます。迷子札にはペットの名前や飼い主さんの連絡先などを記載しておきましょう。
ペットと一緒の避難計画の立て方
災害時にペットと安全に避難するためには、事前に詳細な避難計画を立てておくことが重要です。家族全員で計画を共有し、定期的に見直しを行いましょう。
避難場所・避難ルートの確認
まず、お住まいの地域の避難場所とそこまでのルートを確認しましょう。ペットと一緒に避難する場合、人間だけの避難よりも時間がかかることを考慮して計画を立てる必要があります。
- 確認すべきポイント
-
- 指定避難所の場所と連絡先
- ペット受け入れの可否
- 複数の避難ルート
- ペット同伴時の避難にかかる時間
- 危険箇所や通行困難な場所
お住まいの自治体のホームページや防災マップで最新の情報を確認し、実際に歩いてルートを確認しておくことをおすすめします。
同行避難と同伴避難の違い
ペットとの避難には「同行避難」と「同伴避難」という2つの概念があります。この違いを正しく理解しておきましょう。
- 同行避難
-
災害時に飼い主がペットと一緒に安全な場所まで避難することです。多くの自治体で推奨されている避難方法です。
- 同伴避難
- 避難所で飼い主とペットが同じ空間で生活することです。現在、同伴避難を認めている避難所は限られています。
- 避難の概念の違いに注意
- 多くの避難所では「同行避難は可能だが、同伴避難は不可」という状況です。つまり、ペットと一緒に避難所には行けるものの、避難所内ではペットは別の場所(屋外のテントや専用スペース)で過ごすことになります。
近隣住民・自治体との連携
災害時のペット対策は、個人だけでなく地域全体で取り組むことが効果的です。普段から近隣住民や自治体との連携を図っておきましょう。
- 近隣住民・自治体との連携ポイント
-
- 町内会や自治会でのペット防災対策の話し合い
- 近所のペット飼い主同士での情報交換
- 地域の防災訓練への参加
- ペット同伴可能な避難所の確認
また、自治体が実施するペット防災に関する講習会やセミナーがあれば参加し、最新の情報を入手することが大切です。
ペット預け先の確保
万が一避難所でペットが受け入れられない場合に備えて、複数の預け先を事前に確保しておくことも重要です。
預け先の候補として挙げられるのは、親戚や友人宅、ペットホテル、動物病院、ペット同伴可能な宿泊施設、ペット用シェルターなどです。同じ災害地域だと預かりが難しい可能性も高いので、事前に親戚や友人などに災害時の対応について相談しておき、連絡先を防災グッズと一緒に保管しておきましょう。
- ペットの災害に備えた準備には…
- これらのご紹介した準備を事前にしておくかどうかで、万が一の災害時に安心して過ごせるかどうかの差がでる可能性が高いです。環境省からもペットの災害対策のガイドラインが発行されています。「災害、あなたとペットは大丈夫?人とペットの災害対策ガイドライン<一般飼い主編>|環境省」を印刷しておくと、準備のチェックがしやすいので便利です。災害に備えて確認することをおすすめします。
災害発生時のペットへの対応
災害が発生した際は、まず飼い主さん自身の安全を確保した上で、ペットの安全確保に努めることが重要です。慌てずに適切な判断を行いましょう。
災害発生時の基本的な行動原則(共通の初動対応)
災害の種類に関わらず、災害発生時には以下の基本的な行動原則を守りましょう。
1. 飼い主の安全確保が最優先
まず、飼い主さん自身の安全を確保することが最も重要です。飼い主さんが怪我をしてしまっては、ペットを守ることができません。
2. ペットの所在確認
安全を確保したら、すぐにペットの所在を確認します。災害時、ペットは恐怖からどこかに隠れてしまうことがあります。
3. ペットを落ち着かせる
ペットが混乱している場合は、落ち着いた声で名前を呼び、安心させてあげましょう。飼い主さんの不安がペットにも伝わるため、できるだけ冷静に行動することが大切です。
4. 安全な場所への移動
ペットを安全に保護したら、より安全な場所に移動します。この際、必ずリードを付けるか、ケージやキャリーに入れるなどして、ペットが逃げ出さないよう注意しましょう。
地震・台風・洪水時の対応ポイント
災害の種類によって、注意すべきポイントが異なります。それぞれの災害に応じた対応を理解しておきましょう。
地震の場合
- 揺れが収まるまで、ペットと一緒に安全な場所で身を守る
- ガラスの破片や倒れた家具からペットを守る
- 余震に備えて、ペットにリードを付けておく(リードが必要なペットの場合)
- エレベーターは使用せず、階段で避難
台風の場合
- 事前の避難を検討(早めの判断が重要)
- 強風でペットが飛ばされないよう注意(風が出ている中で避難する場合)
- 停電に備えて、ペット用品を準備
- 窓ガラスの飛散に注意
洪水の場合
- 浸水前の早期避難が重要
- 水位の上昇に注意しながら避難
- 極力ペットはケージやキャリーに入れて避難
- 避難後も衛生状態に注意
ペットの安全確保と避難誘導
災害時にペットを安全に避難させるためには、適切な誘導方法を知っておくことが重要です。
小型犬・猫の場合
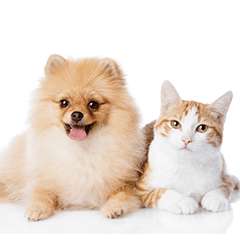
- ケージやキャリーに入れて運ぶのが最も安全
- ケージやキャリーがない場合、しっかりとリードを付けて抱えて避難
- ペットが隠れて出てこない場合は、好物を使って誘い出す
中・大型犬の場合

- しっかりとしたリードとハーネスを装着
- 飼い主の左側につけて歩かせる
- 興奮している場合は、短いリードで制御
複数のペットがいる場合

- 優先順番を決めて無理のない範囲で避難
- 家族で役割分担を決めておく
- 頭数が多い場合、すべてのペットを一度に運ぼうとしない
パニック状態のペットへの対処
災害時、ペットがパニック状態になることは珍しくありません。
適切な対処方法を知っておきましょう。
- パニック状態の症状
-
- 激しく鳴く、吠える
- 震える、息が荒くなる
- 隠れて出てこない
- 攻撃的になる
- 失禁してしまう
- 対処方法
-
- 落ち着いた声で名前を呼ぶ
- 無理に触ろうとしない
- 安全な場所で時間をかけて落ち着かせる
- 普段使っているタオルやおもちゃを近くに置く
- 症状がひどい場合は、専門家に相談
重要なのは、飼い主さん自身が冷静さを保つことです。飼い主さんの不安がペットに伝わり、さらにパニック状態を悪化させる可能性があります。災害時に冷静に対処するのはなかなか難しいですが、大切な家族であるペットを守るために安心できるような対応を心がけましょう。
避難所でのペット飼育
避難所での生活は、ペットにとって大きなストレスとなる可能性が高いです。他の避難者との共同生活を円滑に行うため、適切なマナーとルールを守ることが重要です。
避難所のペット受け入れ状況
避難所でのペット受け入れ状況は、自治体や施設によって大きく異なります。事前に確認しておくことが重要です。
- 受け入れ可能な避難所の特長
-
- ペット専用スペースが設けられている
- 屋外にペット用テントがある
- ペット飼育に関するルールが明確
- 受け入れが困難な避難所の特長
-
- 食品を扱う施設(学校の調理室など)
- 医療施設
- アレルギーを持つ避難者が多い場合
避難所でペットが受け入れられない場合は、事前に確保しておいた預け先に連絡を取るか、車中泊を検討する必要があります。車中泊を行う場合は換気・温度管理・防犯に留意し、熱中症やエコノミークラス症候群のリスクに注意するようにしましょう。
避難所でのマナーとルール
避難所でペットと生活する際は、他の避難者への配慮が不可欠です。以下のマナーとルールを守りましょう。
- 基本的なマナー
-
- 他の避難者への挨拶と理解を求める
- ペットの鳴き声や臭いに注意
- 排泄物の適切な処理
- 定期的な健康チェック
- ケージ等で管理し、放し飼いにしない
- 避難所での生活ルール
-
- ペット専用スペースでの飼育
- ペット立ち入り禁止の区域に連れて行かない
- ワクチン接種証明書の提示
- 他のペットとのトラブル回避
これらのマナーやルールを守ることは、避難所での円滑な共同生活を実現するために大切です。一部自治体ではペット受け入れの事前登録・台帳整備があるため、平時から確認・登録をするようにしましょう。受け入れ条件(ケージ必須、ワクチン証明、口輪携行等)についても事前確認することが重要です。
ペット専用スペースでの生活
避難所によっては、ペット専用のスペースが設けられることがあります。このスペースでの生活について理解しておきましょう。
- ペット専用スペースの特長
-
- 屋外または体育館の一角などに設置される
- ケージやテントでの飼育となる
- 他のペットとの共同生活になる
- 飼い主が交代で管理する可能性がある
- 生活する上での注意点
-
- ケージ内を清潔に保つ
- 適度な運動時間の確保
- ストレス軽減のための工夫
- 他のペット飼い主さんとの協力
- 体調変化への迅速な対応
ペット専用スペースでは、限られた空間での生活となるため、ペットのストレス管理が特に重要になります。
他の避難者との共生
避難所では、ペットを飼っていない人も多く避難生活を送っています。互いに配慮し合い、理解し合うことが大切です。
- 配慮すべきポイント
-
- 動物アレルギーを持つ人への配慮
- 動物が苦手な人への理解
- 子どもたちや高齢者への配慮や安全確保
- 共有スペースでの行動
- コミュニケーションの取り方
-
- 避難所到着時の挨拶
- ペット飼育に関する説明
- 困りごとがあれば相談
- 感謝の気持ちを忘れない
- 積極的な避難所運営への協力
避難所での生活は、誰にとっても大変なものです。お互いに思いやりの心を持ち、助け合うことで、より良い避難生活を送ることができます。
ペットの防災や災害に関するよくあるご質問
ペットの防災対策や災害時の対応について、飼い主の皆さんから寄せられる質問やペット保険の補償対象になるか、など質問にお答えします。
災害時のケガや病気はペット保険で補償されますか?
多くのペット保険では、災害による傷病は補償対象外となっています。地震、津波、台風、洪水などの自然災害が直接的な原因となったケガや病気については、保険金が支払われない場合が一般的です。
災害時にペットに関する補償が受けられない場合が多いため、火災保険や地震保険などで別の損失に備えておくことで、ペット関連の費用に充てる資金の余裕が生まれ、より安心です。災害に備えるには、火災保険や地震保険への加入を検討することをおすすめします。
火災保険や地震保険の見直しや加入のご検討は、オリジナル比較システムで保険料と補償内容を簡単に比較できる「i保険の火災保険・地震保険の比較サイト」をご活用ください。
災害時のペットの治療費は全額自己負担となる可能性が高いため、日頃からペットの健康管理を徹底し、日常的なケガや病気はペット保険で備え自己負担を減らし、災害に備えた資金の準備も大切です。
普段からできるペットの防災訓練はありますか?
災害時に慌てず行動できるよう、日頃から以下のような防災訓練を行いましょう。
- 基本的な訓練
-
- ケージやキャリーに慣れる練習
- リードでの避難経路の歩行
- 「待て」「おいで」などの基本コマンドの徹底
- 車での移動に慣れる練習
- 他の人や動物との接触練習
- 月1回程度の定期訓練
-
- 防災グッズの点検と交換
- 避難経路の確認
- 家族での役割分担の確認
- ペットの健康チェック
これらの訓練は、ゲーム感覚で楽しみながら行うことで、ペットも飼い主さんもストレスなく身につけることができます。
ペット用防災グッズはどこで購入できますか?
ペット用防災グッズは以下の場所で購入できます。
- 実店舗
-
- ペットショップ
- ホームセンター
- 100円ショップ(一部商品)
- ドラッグストアなど
- オンライン
-
- ペット用品専門サイト
- 総合通販サイト
- メーカー直販サイトなど
最近では、ペット用防災グッズをセットにした商品も販売されており、初めて準備する方にはおすすめです。購入の際は、ペットの大きさや特性に合わせて選ぶことをおすすめします。
避難所でのペットの受け入れ状況はどこで確認すればいいですか?
避難所でのペット受け入れ状況は、以下の方法で確認できます。
- 確認方法
-
- 自治体のホームページ
- 防災マップやハザードマップ
- 自治体の防災担当課への確認
- 町内会や自治会での情報収集
- 動物愛護センターへの問い合わせなど
情報は変更される可能性があるため、定期的に最新の情報を確認することが大切です。また、複数の避難所の状況を把握しておくことで、より柔軟な対応が可能になります。
災害時にペットとはぐれた場合どのように対応すればいいですか?
ペットとはぐれてしまった場合は、以下の対応を速やかに行いましょう。ただし大規模な災害の場合は連絡手段も限られるため現場の状況に応じてできる範囲の対応をしましょう。
- 初期対応
-
- 警察署への届け出
- 保健所・動物愛護センターへの連絡
- 近隣住民への聞き込み
- インターネット掲示板での情報提供
- 動物病院への連絡
- 継続的な対応
-
- 定期的な捜索活動
- チラシの配布
- SNSでの情報発信
- ボランティア団体への協力依頼
ペットとはぐれてしまった場合でも、事前にマイクロチップなどの身元を確認できる対策をすることで、飼い主さんの元へ返還できる可能性が高まります。犬や猫のマイクロチップに関する詳細は、「犬・猫のマイクロチップは義務?装着のメリット・デメリットと登録方法」もご覧ください。
また、犬や猫の迷子対策や捜索方法についてまとめた記事もご活用ください。
避難時にペットが嫌がる場合どのように対処すればいいですか?
ペットが避難を嫌がる場合は、以下の方法で対処しましょう。
- 対処方法
-
- 落ち着いて、優しい声で話しかける
- 好物やおやつで誘導する
- 普段使っているタオルやおもちゃを持参
- 無理に引っ張らず、時間をかけて説得
ただし、生命に危険が及ぶ緊急時は、ペットが嫌がっても安全を最優先に避難する必要があります。大事なのは、いざというときに対応できるように、日頃から準備や避難訓練をしておくことです。
その他のペット保険に関するご質問についてはペット保険のよくあるご質問ページも確認ください。
よくあるご質問まとめ|日頃の備えで災害時もペットの命を守る
ペットの防災対策は、災害が発生してから慌てて準備するものではありません。日頃からの備えと準備こそが、災害時にペットの命を守る最も確実な方法です。
大切な家族の一員であるペットを災害から守るのは、飼い主の責任です。「備えあれば憂いなし」という言葉通り、しっかりとした準備により、災害時でもペットと一緒に安全に避難し、避難生活を送ることができます。
災害はいつ発生するかわかりません。今この瞬間から、ペットの防災対策を始めていきましょう。小さな準備の積み重ねが、いざというときにペットの命を救うことにつながります。
また、ペット保険への加入により、日常的な病気やケガに備えておくことで、災害時以外の医療費負担を軽減し、防災資金の確保にもつながります。複数の保険会社を比較検討して、ご家庭に最適なペット保険を見つけてください。
この記事の情報は一般的な内容を基にしており、個々のペットの状況によって対応は異なります。ペットの避難所受け入れに関するご不明な点は、お住いの自治体にご相談ください。また、ペット保険に関する内容は各保険会社の最新の約款をご確認ください。
- 執筆者
- 染谷 弥幸(1級ファイナンシャル・プランニング技能士/株式会社アイ・エフ・クリエイト)
「安心できる金融商品選びをわかりやすくカンタンに」という当社のミッションを胸に、お客様が自分に合った商品をみつけるための情報をわかりやすく紹介します。